司法書士がChatGPTを活用する際の注意点とメリットとは?丁寧解説

業務効率化やサービス向上のために、ChatGPTを活用したいと考えている司法書士の方も多いでしょう。
しかし、名前は聞いたことがあるものの、司法書士の業務にどのようにChatGPTを活用できるのか、また、どのようなリスクがあるのかが分からない方もいるかもしれません。
本記事では、ChatGPTの活用方法に加え、司法書士がChatGPTを安全に活用するための注意点とメリットを丁寧に解説します。
- 司法書士がChatGPTを活用するメリット
- ChatGPT活用に潜むリスクと注意点
- 司法書士のためのChatGPT導入のステップと運用フロー例
ChatGPTとは何か

ChatGPT(チャットジーピーティー)とは、米国の企業OpenAIが開発した大規模言語モデル(LLM)と呼ばれるAIの一種です。
ユーザーが入力したテキストに対して、まるで人間が会話するかのように自然な文章で回答を生成できることが最大の特徴といえます。
従来のAIチャットボットと比較しても多彩なトピックに対応できるだけでなく、文章作成や要約などの高度なタスクもこなすため、さまざまな業種での導入が進んでいます。
司法書士のような専門職においても、契約書作成や法令リサーチ、クライアントとのコミュニケーション補助など、多岐にわたる業務でChatGPTの活用が期待できます。
しかし一方で、守秘義務をはじめとする法的リスクへの配慮を忘れてはいけません。
基本的なしくみ
ChatGPTは、インターネット上の膨大なテキストデータを事前学習し、人間の「言葉のつながり方」や「文脈」を理解する能力を獲得しています。
単語同士の関係性や文章の構造を数多く学習することで、きわめて自然な文書生成が可能となっています。
ただし、ChatGPT自体は「言語を統計的に推測して並べる」仕組みによって動作しており、必ずしも事実や最新の法令を常に正確に把握しているわけではありません。
AIの学習データには時差や情報の偏りが存在する場合があり、最新の法改正や個別事情には対応しきれないこともあります。
したがって、司法書士が専門的な業務に利用する際には、最終的な精査や監修が不可欠です。
ChatGPT活用のメリット
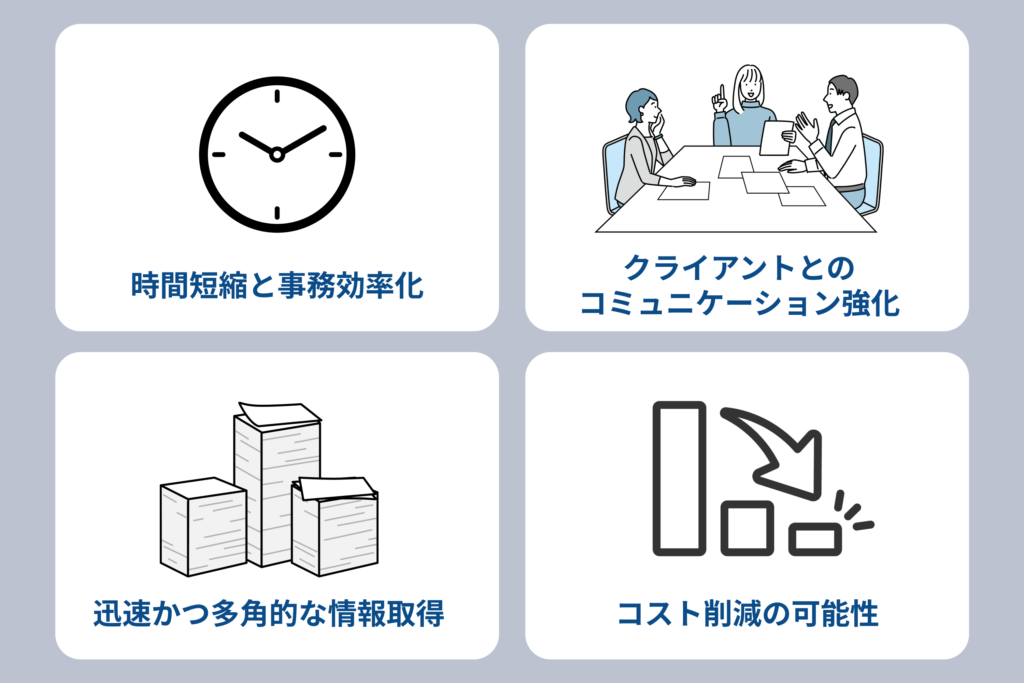
ChatGPTを活用すると、以下のようなメリットがあります。
- 時間短縮と事務効率化
- クライアントとのコミュニケーション強化
- 迅速かつ多角的な情報取得
- コスト削減の可能性
時間短縮と事務効率化
ChatGPTを業務に導入する最大のメリットのひとつが、「時間短縮」です。
司法書士の業務には、契約書や登記申請書などの書類作成、クライアントとのやり取り、法令リサーチなど、多数の事務作業が存在します。
これらのうち、定型的でパターン化しやすい箇所については、ChatGPTが下書きを自動作成することで大幅な工数削減が可能です。
たとえば、何度も同じような契約条項を書く場合、あらかじめChatGPTに必要な要素を入力し、下書き文面を得たうえで微調整を行うことで、作業時間を短縮できます。
また、補助者やスタッフへの作業指示の一部をAIに任せることで、専門家としての本来の業務に集中しやすくなるのです。
クライアントとのコミュニケーション強化
司法書士には、クライアントの相談内容を正確に把握し、適切な手続きを案内するコミュニケーション能力が求められます。
しかし、クライアントからの初期問い合わせや簡易的な質問への対応は、時間や手間がかかることも多いでしょう。
ChatGPTを活用すれば、まずは自動的に定型回答を提示し、その後に専門家が精査して補足説明を加えるというフローを構築できます。
さらに、メールやチャットでの文面をChatGPTに下書きさせることで、文調の統一や誤字脱字の防止につながるメリットもあり、クライアント一人ひとりに丁寧かつ迅速に対応できる体制づくりが可能になります。
迅速かつ多角的な情報取得
ChatGPTの特筆すべき点は、ユーザーが質問した内容に対して多角的な情報を提供できることです。
司法書士は、登記や債務整理、裁判事務など多岐にわたる業務範囲を扱うため、普段は扱わない分野の情報が必要になるケースもあるでしょう。
ChatGPTから得られるヒントは、法令・判例リサーチの入り口として活用でき、業務の幅を広げる可能性を秘めています。
特に、大量の文献や資料から必要なポイントをピックアップして要約する作業は、時間と手間がかかりがちです。
ChatGPTに「〇〇法の概要を端的に示してください」「過去の判例の傾向をリストアップしてください」などと尋ねることで、大まかな道筋をつかみやすくなるでしょう。
ただし、後述するように情報の真偽や最新性の確認が欠かせない点は要注意です。
コスト削減の可能性
ChatGPTを適切に活用できれば、コスト削減にも寄与します。
たとえば、一定の文書作成やリサーチを外部に委託していた部分をAIツールが代替することで、外注コストを抑えられるかもしれません。
また、従来であればスタッフや補助者が長時間を費やしていた業務が短時間で済むようになれば、人件費の最適化にもつながります。
ChatGPT活用に潜むリスクと注意点
司法書士がChatGPTを活用する際に最も重要視しなければならないのは、守秘義務や法令に関するリスクへの対策です。
以下では、具体的なリスクと注意点を順に解説します。
- 守秘義務違反のリスク
- 情報漏えいの可能性
- 法的アドバイスの誤用・責任問題
- 判例・法令のアップデート遅延による誤回答
- 著作権・商標権などの知的財産リスク
守秘義務違反のリスク
司法書士には、司法書士法によって定められた守秘義務が課されています。
クライアントから得た個人情報や相談内容を、第三者に漏らすことは厳しく制限されており、当然AIサービスへの情報入力にも注意が必要です。
ChatGPTのようなクラウド型AIは、入力されたテキストデータをサーバーで解析して応答を生成する仕組みを採っています。
そのため、クライアントを特定できる情報や事件の詳細を安易に入力すると、誤って情報漏えいにつながる可能性があります。
そのため、「登記申請人のフルネームや住所」「債権者の詳細情報」などをそのまま入力しないことが鉄則です。
代わりに、抽象化・匿名化した情報を入力して、守秘義務を厳守しつつAIの助言を得るのが良いでしょう。
情報漏えいの可能性
ChatGPTに入力したデータは、サービス提供元のサーバー内で一定期間保存・学習に利用されることがあります。
したがって、クライアントの詳細情報や内部文書をうっかりアップロードした結果、外部からアクセスされるリスクはゼロではありません。
情報管理には細心の注意を払いましょう。
法的アドバイスの誤用・責任問題
ChatGPTは、あくまで言語モデルであり、司法書士の資格や弁護士資格を持っているわけではありません。
もしAIが間違った法的アドバイスを生成し、それを鵜呑みにしてクライアントに案内してしまえば、重大なトラブルや責任問題に発展する恐れがあります。
特に、最新の法令改正や実務上の手続き詳細は頻繁に変わることがあり、AIがその全てを正確に把握している保証はありません。
ChatGPTを参考情報のひとつとして活用するに留め、最終的な確認と判断は専門家である司法書士自身が行うことが必須です。
判例・法令のアップデート遅延による誤回答
AIモデルは学習元データに依存しており、学習時期以降に施行された法令や判例には対応できないケースがあります。ときには古い情報がそのまま出力されることもあるため、常に最新の法令集や公式サイト、信用できる法律データベースと照合する習慣をつけるべきです。
また、判例の解釈や適用範囲は実務上の考え方とAI回答が異なることも珍しくありません。
ChatGPT任せにするのではなく、あくまでも補助ツールとして位置づけるのが望ましい姿勢といえます。
著作権・商標権などの知的財産リスク
ChatGPTが生成した文章や資料のなかに、他人の著作物を無断で引用した可能性が含まれているリスクも否定できません。
大規模に学習しているとはいえ、万が一AIの回答に他者の著作権を侵害する表現や商標名の不適切な使用が含まれていた場合、そのまま利用するとトラブルの原因になり得ます。
とくに、事務所のWebサイトや広告などに流用する際は、最終的に司法書士あるいは専門家がチェックし、問題がないかを確認しましょう。
具体的な活用方法と注意すべきポイント
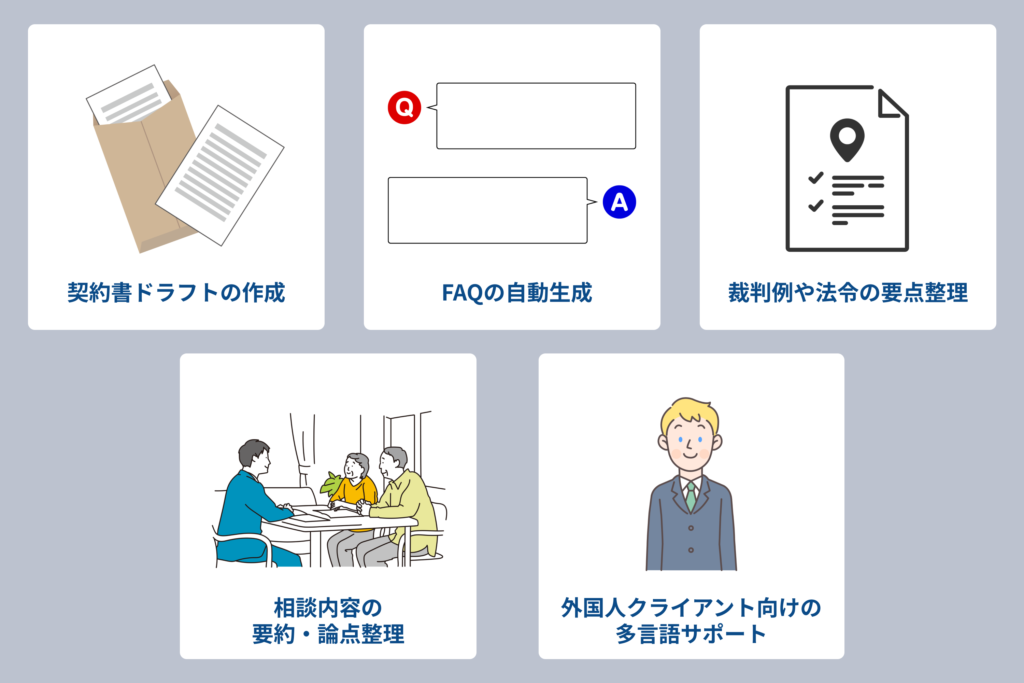
以下では、司法書士業務に役立つ具体的なChatGPT活用方法と、注意点を解説します。
- 契約書ドラフトの作成
- FAQの自動生成
- 裁判例や法令の要点整理
- 相談内容の要約・論点整理
- 外国人クライアント向けの多言語サポート
契約書ドラフトの作成
司法書士業務では、遺産分割協議書や賃貸借契約書など、さまざまな契約書類を扱います。定型的な契約書であれば、ChatGPTに「家賃〇〇円、契約期間〇年の賃貸借契約のドラフトを作成して」と指示するだけで、大枠のテンプレートを得られるでしょう。
ただし、具体的な当事者情報や物件情報などを入力する際には、機微情報を伏せる工夫を忘れないようにしてください。
AIが出力したドラフトはあくまで素案であり、条文の細部や法的効力の確認は専門家が担う部分です。
最終チェックを怠れば、思わぬ抜けや誤りに気づかないままクライアントに提供してしまうリスクが高まります。
FAQの自動生成
多くの事務所サイトでは、よくある質問(FAQ)を設けて、来所前に必要な基本知識を提供しているケースが増えています。
ChatGPTに「不動産登記でよくある質問と回答を作成してほしい」などと依頼すると、ある程度網羅的なFAQが自動生成されるため、作業効率が大幅にアップします。
ただし、利用者がこれを見て誤解を生じないように、各Q&Aの正確性を人間が最終的にチェックし、分かりやすい言葉にリライトすることが必要です。
過度に専門用語が多い場合や、実際の手続きと異なる回答が混ざっている場合は修正を行いましょう。
裁判例や法令の要点整理
ChatGPTは長文の要約や論点整理を得意としています。
法令全文や判例の判旨をAIに引用したうえで、「この裁判例の要点を3行でまとめてください」と指示すれば、短時間で概略をつかむことが可能です。
ただし、守秘義務や機密性の高い情報が含まれる判決文であれば、個人情報を除去し、事件名を伏せるなどの工夫が必要です。
また、出力結果を鵜のみにせず、原文に必ず目を通して最終的に自分で確認することが欠かせません。
相談内容の要約・論点整理
クライアントからの相談内容が複雑なケースや、複数の依頼が重なるとき、ChatGPTを使ってヒアリング内容を簡潔に要約させるのも一案です。
事前に録音やテキスト化した相談内容を箇条書きにまとめ、AIに「この相談の争点を洗い出して」と依頼すると、見落としがちな論点に気づくきっかけになるかもしれません。
ただしここでも、クライアントの個人情報や事件の詳細を丸ごと入力するのではなく、抽象度を高めた概要だけ、論点だけを要約したテキストを入力するなどの工夫が求められます。
外国人クライアント向けの多言語サポート
外国人クライアントが増えている事務所の場合、多言語対応は大きな課題のひとつでしょう。
ChatGPTは多言語の文章生成にも対応しており、簡易的な翻訳や外国語での案内文作成に役立ちます。
たとえば「日本語で作成した文章を英語や中国語に翻訳してほしい」と依頼すれば、一定レベルの質で多言語文書が作成できます。
ただし、法律や契約に関する表現は微妙なニュアンスが重要であり、誤訳が致命的な結果を生む可能性も高いため、最終的には専門家やネイティブスピーカーによる校閲が望ましいです。
ChatGPTを安全に使うための注意点
ChatGPTはとても便利ですが、使い方を間違ってしまうとリスクがあります。安全に使うための方法を、しっかりと確認しましょう。
- 入力データの取扱いルールの制定
- プライバシーポリシーと利用規約の確認
- セキュリティ面の確保
- AI回答を鵜呑みにしない検証プロセス
入力データの取扱いルールの制定
まずは事務所内で、「AIに入力してよい情報/絶対に入力してはいけない情報」を明確化しましょう。
クライアントを特定できる固有名詞や案件の詳細情報は入力禁止とし、必要に応じてダミー情報や抽象化したデータを使う運用ルールを設定します。
また、スタッフや補助者が増えるほど、情報をうっかり入力してしまうリスクが高まるので、事前に全員が共通のルールを認識することを徹底しましょう。
プライバシーポリシーと利用規約の確認
ChatGPTを提供するOpenAIなどのサービス利用規約やプライバシーポリシーは、必ず目を通したうえで利用する必要があります。
無料版でも有料版でも、入力されたデータが学習に使われる可能性があります。
万一、情報漏えいが発生した際の対処や補償範囲など、契約内容を正しく理解しておくことが重要です。
セキュリティ面の確保
司法書士の業務では、クライアントの個人情報や機密情報を取り扱うため、セキュリティ対策は欠かせません。
ここでは、ChatGPTを安全に利用するための方法をわかりやすくご紹介します。
1・オプトアウト機能(Chat History & Training)をオフにする
ChatGPTには、ユーザーとのやり取りを学習に使わない「オプトアウト機能」があります。
英語版では「Chat History & Training」、日本語版では「すべての人のためにモデルを改善する」をオフにすると、入力内容がOpenAIのサーバーに学習データとして蓄積されにくくなり、情報漏えいリスクが下がります。
司法書士事務所でChatGPTを使う場合は、「個人情報や機密事項はオプトアウト機能をオフにしてから入力する」など、ルールを決めて周知しておきましょう。
2.ChatGPT Enterpriseプランの利用を検討する
より高いレベルのセキュリティを求めるなら、法人向けのChatGPT Enterpriseプランを検討する方法もあります。
このプランでは、組織での使用を想定しており、利用状況を監視・分析できるダッシュボードや、やり取りを学習に使わない仕組みが整っているのが特長です。
また、データが暗号化されるため、外部に漏えいするリスクをさらに抑えられます。
ただし、費用がかかるため、「導入コスト」と「業務効率化で得られるメリット」のバランスをよく検討する必要があります。
もちろん、ウイルス対策ソフトの導入や公共のWi-Fiは使用しないようにするなど、基本的な対策も確認しましょう。
AI回答を鵜呑みにしない検証プロセス
ChatGPTは非常に高度な文章生成能力を持ちますが、その回答が正しいとは限らないという前提を忘れてはいけません。
具体的には、以下のようなプロセスを設けることが有効です。
- AIによる下書き作成
- 人間の専門家(司法書士)の校閲
- 最終的な法令や書式確認
このプロセスを徹底することで、誤回答や誤情報の使用リスクを最小限に抑えられます。
定期的なAI利用ガイドラインの見直し
AI技術は日進月歩であり、利用規約や法的要件も随時変化します。
したがって、一度決めたガイドラインを永遠に使い続けるのではなく、定期的に見直す仕組みづくりが必要です。
たとえば、年に一度のリスク評価や社内研修を通して新しい機能や改正法に対応する、新入スタッフ向けに簡易マニュアルを作るなど、事務所全体でのルール周知を欠かさないようにしましょう。
ChatGPT導入のステップと運用フロー例

ChatGPTを導入するにあたっては、焦らずにひとつずつ確認していくことが重要です。
慌てて導入すると、目的があやふやになったり情報漏えいの原因になることも考えられます。
- 導入前の準備
- 試験運用と効果測定
- 本格運用時のルール作り
導入前の準備
ChatGPTを本格的に導入する前に、まずは事務所内のニーズを洗い出すことが重要です。
どの業務プロセスを効率化したいのか、守秘義務の観点からどのような対応が必要なのかを明確にしましょう。
また、スタッフ間でAIリテラシーに差がある場合、簡単な勉強会を実施するなどして全員が基本的な操作方法やリスクを理解できる体制づくりを行います。
試験運用と効果測定
導入初期は、限定的な範囲で試験運用を行うのが望ましいでしょう。
たとえば、契約書の定型部分だけをAIに下書きしてもらい、スタッフが修正・評価するなどの方法です。
この際、業務時間の削減効果やミスの減少率など、数値化できる指標を設定しておくと、後の本格導入の際に説得力が増します。
本格運用時のルール作り
試験運用を経てある程度のメリットとリスクが把握できたら、本格運用に向けて詳細なルールづくりを進めましょう。
- 入力データの管理方法:個人情報や機密事項の匿名化ルール
- 最終チェック体制:AIが生成した文書を誰が検証し、どのようなフローで校正するか
- データ保存期間:AIへの入力ログをどの程度保管するか、または即時削除するか
これらを明文化し、事務所の全員が共有しておくことで、万一のトラブル発生時にもスムーズな対処が可能となります。
ChatGPTのリスクを理解して業務改善に役立てよう
ChatGPTは、文章生成や情報リサーチなど、多岐にわたるサポートを実現する革新的なAIツールです。
司法書士がその力を正しく活用すれば、事務作業の効率化やクライアント対応の質向上につなげられる大きな可能性があります。
しかし一方で、守秘義務違反や法令リサーチの誤り、著作権侵害リスクなど、多くの注意点が存在することも事実です。
最終的に、ChatGPTを使いこなす鍵となるのは司法書士自身の専門性と責任感です。
AIをあくまでも「効率化のための支援ツール」と位置づけ、最終判断は専門家としての知識と経験に基づいて行う姿勢が求められます。
適切な利用ルールとセキュリティ体制を構築し、ChatGPTのリスクを十分理解したうえで業務改善に役立てていきましょう。
